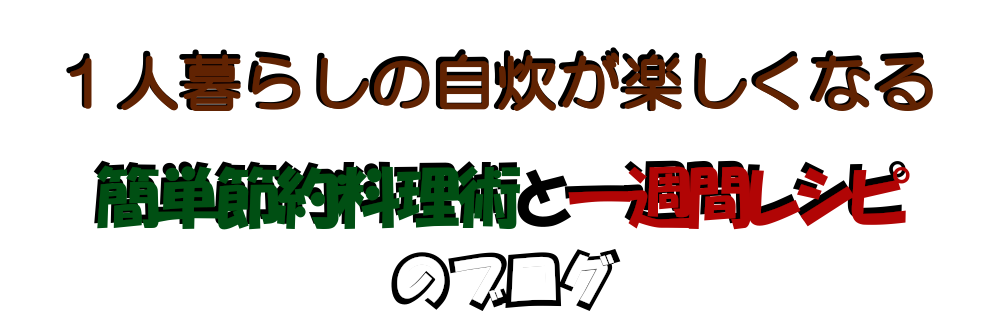食材の保存方法

買い物をした食材はすぐに全部食べるわけではありませんよね。食べない分は冷蔵庫にしまったりしておくと思いますが、どんな食材にも賞味期限があります。仮に設定されていなかったとしても、いつかは腐るものです。
いつのまにかこれ腐っちゃった!
なんてこともあるのではないでしょうか?
このブログでは食材使い切りをベースとしていますのでそういったことはないと思いますが、テーマである「一週間」というのは、実のところ食材的には微妙な時間ではあります。
はっきりと言ってしまえば、買った肉や魚がそのままの状態で一週間保つことはない、と言えるでしょう。
では7日目のレシピは腐ったものを使うのか。
そんなわけはありません。
料理には、無数に食材を長持ちさせる方法が存在します。
保存という技術そのものも料理の一つととらえて構わないでしょう。
ここでは、そんな食材の保存方法をいくつかご紹介したいと思います。
生のまま保存する方法
野菜
野菜は比較的長持ちする方です。おそらく適切に保存すればじゅうぶん一週間もたせることはできるでしょう。それでも、野菜も生き物ですので鮮度は落ちていくものですし、環境が悪ければ悪くなるのも早くなってしまいます。
ここではそんな野菜保存のコツを紹介したいと思います。
1、根っこや葉っぱは切り取っておく。
大根やニンジンなどの根菜類には根っこや葉っぱ(ヘタの部分含む)が付いています。じつはこういった根菜は、そのままにしておくと根っこや葉っぱの成長のために可食部からどんどんと水分や栄養を奪ってしまいます。ほんの少しそぎ落としておくだけでいいので、切り落としておくとよいでしょう。
切り落とした後の切り口には、水を含ませて硬く絞ったペーパーをあて、ラップでくるんでおきましょう。
2、葉物野菜は、根っこ(ヘタや茎)の部分を切りおとして水に漬けておくと復活する。
根菜と同じように根っこを切りおとし、その切り口を水に漬けておくと、葉っぱの部分に水分がいきわたり鮮度を取り戻します。その状態で切り口の部分に、水分を含ませて硬く絞ったペーパーを巻いておけば、しばらく鮮度を維持することができます。
それを乾燥しないようにラップか保存バックなどに入れて保存しましょう。
3、濡れたまま保存しない。
どんな野菜でも洗うことはよいのですが、洗って、濡れたそのまま冷蔵庫などで保存してしまうと、付いた水分が野菜の熱を奪い、腐らせてしまいます。
葉物はなるべく葉っぱの部分は濡らさないように、濡れてしまったらしっかりとふき取って、乾燥させてから冷蔵庫に入れましょう。
4、そもそも濡らしてはいけない食材がある
特にキノコ類がその代表です。キノコを洗うのは調理する寸前のみに留め、保存する場合は乾燥したままペーパーなどに包んで傷つくのを防ぎ、保存バックに入れておくことをおススメします。
そこまでしなくても、買ったらパックのまま保存しておくのも手でしょう。
肉
生肉は腐りやすいイメージがありますが、適切に保存することで案外長持ちします。
ただし一つ、生のまま保存する際に気を付けたいのは、他の食材に触れないようにするということです。
生肉の表面には様々な菌がいます。それは基本的に食中毒を引き起こすものです。生肉を扱う際は、その生肉が触れるものに注意を払ってください。特に切ったまな板や包丁などは、よく洗剤で洗ったあと漂白し、アルコールで除菌することを徹底した方が良いです。
その基本を守りながら、以下の方法で保存すると長持ちします。
1、油でマリネする
生肉は空気に触れた部分から傷んでいきます。なので、表面を油でコーティングすることで空気と触れることを防ぎます。
2、塩や砂糖で表面を殺菌する。
塩や砂糖には殺菌効果が期待できます。生肉の表面にある細菌を殺すことで腐敗を防ぎます。
またこの方法は同時に味を加えることもできるので、調理も同時にこなすことができます。
3、調味液に漬ける。
塩や砂糖で殺菌するのと同じ考え方で、そこにさらに望んだ味を付加するやり方です。唐揚げなどで使える方法ですね。
ただし漬けすぎると味が濃くなるので注意!
4、冷凍保存する。
肉に何も加工を施したくない、だけどすぐには使わない。そんな時は凍らせてしまうのが一番です。下ごしらえをしてから凍らせれば、解凍してすぐに使うことができるのでおススメです。
魚
正直、魚が一番傷みやすいです。あまり長い時間生のまま置かないのがベストですが、それでも長持ちさせる方法はあります。
1、内臓がある魚は取っておくのが良い。
一番先に痛むのが内臓の部分です。切り身ではなく一匹で買った場合は、内臓を取ってしまうのが良いでしょう。
2、油でマリネする。
肉と同じ理由と方法です。
3、塩や砂糖で殺菌する。
こちらも肉と同じ理由と方法ですね。魚の場合、塩を振ることで水分が出て、それをふき取ることで生臭さを取ることができるので、おススメです。
4、冷凍保存する
肉と同様に魚も冷凍できますが、解凍時の傷みが肉よりも激しいので、味の面であまりおススメはできませんね。
加熱して保存する
コンフィという加熱方法
端的に言うと低温で加熱する方法です。
水分の損失やうまみの損失が少なく、コンフィから焼いたり揚げたりもできるので、加熱しつつも調理の幅を狭めません。またこの状態で冷凍もできますから、使い勝手はいいと思います。
家でコンフィする場合、基本は、
1、表面に塩をする。少しおいて水分をふき取る。
2、密閉できる保存バックに入れ、油を少々加える。
3、水をためたボウルなどを使って、バックの中の空気を抜いて密封する。
4、湯を沸かし火を止めたら、バックを入れて20分ほど放置する(大きい場合は30分ほどかかる)
一度沸騰した湯につけているので表面は殺菌されます。
肉でも魚でもできます。
燻製という加熱方法
これはもう、少し番外編的ですが、個人的には燻製もおすすめです。
まとめ&心強い助っ人
このブログでは1週間を1セットとしているわけですが、やはりどうしても続けて7日間というわけにはいかない現実もあると思います。そんな場合にはここでの保存方法を実践してもらうことで、有効に食材を使うことができると思います。
また、技術の進んだ今の時代、なにも加工しなくても保存期間を長くすることができる冷蔵庫も存在します。道具にこだわる人やあくまでも鮮度を重視する人は、そんな冷蔵庫を使うのも手かもしれませんね。
さて、保存方法が分かっても、それをどうやってしまうかが次の問題です。
それを解説しているのがこちらです!